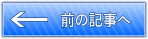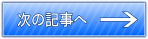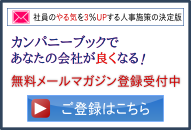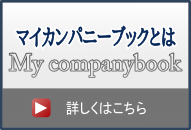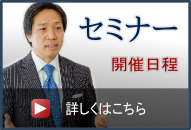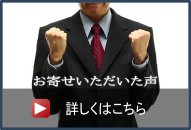第26話 懲戒の正しい使い方とは?
「無断欠勤を何回やったら辞めさせられますか」
経営者の方から、このようなご質問を受けることがあります。欠勤という行為は、本来の約束が守られなかったということです。
ただし、辞めさせる、つまり、解雇ということになると、いろいろな問題が出てきます。この事案の場合、いきなり解雇をすることはできませんから、その手前に改善手続が要るようになります。
ここで大きな意味を持つのが懲戒です。無断でなくても、欠勤が一定程度繰り返されれば、他の社員の士気が下がり、会社の秩序を乱すことになって、懲戒の対象になります。そこで、最初に対応するときには、いきなり懲戒ではなく、注意や指導をするべきです。
注意や指導をしたにもかかわらず、また繰り返すなど、十分な改善が認められない時に初めて懲戒を行うということになります。その懲戒は、けん責のように一番軽いものを選ぶことになります。そして、何度注意しても改善されないということであれば減給の処分という流れです。つまり、軽い処分を繰り返すことになります。これが、改善のチャンスを渡すということです。要するに、この処分は、社員との労働契約が続いていくことが前提となります。
欠勤の場合は、けん責とか減給といった懲戒が改善指導になります。この指導を何か月単位で行って、記録を残しても、結果として改善しなければ、やむを得なく解雇を選ぶことになります。
改善指導で問題となるのは、本当に改善させようとする意思がないと取られてしまうことです。改善指導を行って、その社員をもう一度有効に活用しなければ意味がありません。したがって、最初に解雇ありきで手続をすると、改善指導の記録が残っていても、改善する意思がないと取られかねません。
言うまでもなく、懲戒は約束です。つまり、就業規則などに書いてあるものだけに権限があります。なので、就業規則に書いていなければ改善手続も踏めないということになってしまいます。
また、懲戒には、いろんな行為パターンがありますし、現時点では考えられなくても、将来、新しいものが加わる可能性は十分あります。それを見越して、書いておかなければいけません。だから、一般条項として「上記に類する事項」などと入れておく必要があります。
懲戒を「罰」としての機能はもちろん、「改善手続」として使う場合は就業規則の整備が欠かせません。あなたの会社の就業規則は、大丈夫でしょうか?